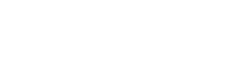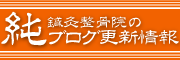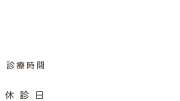熱はないのに「せきやたんが出る」そんな症状でお悩みの方が多い季節です。
今月は「せき・たん」についての情報をお送りします。
今月は「せき・たん」についての情報をお送りします。
せき・たん ~せき、のどの痛みを鎮め、体を潤すものを食べる~
 しつこいせきとたんは、必ず原因を調べる
しつこいせきとたんは、必ず原因を調べるせきは、気道が何らかの刺激を受けたときにおこる、防御的な運動です。たんは細菌やごみが分泌物とまじったものです。せきは、乾いたせき、湿ったさきの2つに分けられます。
乾いたせきは、からぜきといわれ、コンコン、カンカンといった幹二で、たんはほとんど出ません。かぜや気管支炎、肺炎の初期にみられます。乾いたせきが長く続くときは、肺結核の可能性もあります。
湿ったせきは、ゴホンゴホン、ゼイゼイといい、たんを伴います。乾いたせきの症状が進んで、湿ったせきに変わることもよくあります。肺の病気、気管支拡張症、心臓弁膜症の場合にもみられます。
せきが激しいときや、発作的におこったとき、たんに血がまじったり、緑や褐色のたんが出るときは、できるだけ早く医師の診断を受けましょう。また胸の痛み、頭痛、発熱などの症状にも注意します。
家庭では体力を消耗しないように、栄養のある食事を心がけます。
ねぎ(せきどめ、たんきりの妙薬)
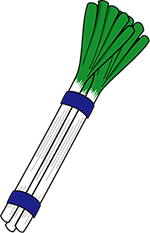 かぜの熱によく効くねぎは、せきどめにも効果があります。ねぎの栄養部分は青い葉のほうに多く、白い部分にはビタミンAが含まれていませんが薬効があり、かぜやせき、たんきりなどに効力を発揮します。
かぜの熱によく効くねぎは、せきどめにも効果があります。ねぎの栄養部分は青い葉のほうに多く、白い部分にはビタミンAが含まれていませんが薬効があり、かぜやせき、たんきりなどに効力を発揮します。ねぎの白い部分だけ使う、ねぎのハチミツ煮をスプーン一杯ずつ、1日に2回食べると、せきを鎮め、たんをきる効果があります。湿布薬としてつかってもせきを鎮めます。
【ねぎのハチミツ煮】
〔材料〕
ねぎ 7本
ハチミツ 60g
水 100ml
〔作り方〕
1.ねぎは白い部分だけを使う。適当な大きさに切り、すり鉢などでよくつきつぶす。
2.なべにうつし、ハチミツと水を加え、まぜる。煮るときは、とろ火であれば、ときどきかきまぜるだけで焦げつかない。
3.弱火でドロドロになるまで煮る。とろみが出るまで煮る。
4.1回にスプーン1杯(約5g)、1日に2回食べる
※ つくときは時間と腕力が必要になります。前もってスピードカッターやミキサーせ粗いみじん切りにしてからつくると良いでしょう
※ 煮るとねぎの甘みが増すことでとても甘く、煮込んであるので、ねぎ特有の臭みや辛みもありません。子供でも食べられます。
しそ(発熱、寒気のあるせきに)
 しその葉と実にはせきどめ、鎮静、鎮痛などの薬効があります。かぜをひいて、発熱と寒気を伴うせきには、しそとしょうがの煎じ汁が効きます。
しその葉と実にはせきどめ、鎮静、鎮痛などの薬効があります。かぜをひいて、発熱と寒気を伴うせきには、しそとしょうがの煎じ汁が効きます。しぞの葉10枚にしょうが5gを加え、300mlの水で半量になるまで煎じてのみ益す。または、しその葉10枚に陳皮(ちんぴ=みかんの皮を乾燥させたものとしょうがを3gずつ加え、600mlの水で煎じます。これを3回に分けて、あたためて飲みます。
なし(のど、肺を潤す)
 熱があって、せきがとまらず、たんもきれないときや、のどに痛みや渇きがあるときには、なしのしぼり汁がよく効きます。なしをすりおろし、ガーゼでしぼった汁を飲みます。
熱があって、せきがとまらず、たんもきれないときや、のどに痛みや渇きがあるときには、なしのしぼり汁がよく効きます。なしをすりおろし、ガーゼでしぼった汁を飲みます。これに、しょうがのしぼり汁とハチミツを加えてあたためるホットジュースもせきとたんに効きます。
うす切りにしたなし1個を冷水につけ、半日ほどおいて、その汁ごと飲むと口の渇きがおさまります。
胃が冷えやすく下痢ぎみの人、冷え性の人、出産後には、食べ過ぎないよう注意しましょう。
【なしとしょうがのホットジュース】
〔材料〕
なし 1個
しょうが ひとかけ
はちみつ 好みで
〔作り方〕
1.なし1個をすりおろして、ふきんでしぼり汁をとる
2.親指大のしょうが1かけをすりおろして汁をとる
3.[1]と[2]をあわせ鍋にいれる。好みにあわせてハチミツをくわえてあたためて飲む
れんこん(かぜのひどいせきに効く)
 せきどめには、れんこん湯が効果的です。
せきどめには、れんこん湯が効果的です。まず、れんこんを皮つきのまま乾燥させます。これをうす切りにし、水で煎じます。これにだいこんあめを加えて、好みの甘さにしたものがれんこん湯です。1日3回飲むと、ひどいせきもおさまります。
また、れんこんを生のまますりおろして、そのしぼり汁をのむのも効果的です。この場合は、きれいに泥を洗い流して、皮をむかずにすりおろします。皮つきのままのほうが薬効があるからです。
【だいこんあめ】
〔材料〕
だいこん 3cmの輪切り
はちみつ(水あめでもよい) 適量
〔作り方〕
1.だいこんを5mm幅の半月切りか、いちょう切りにする。
2.だいこんをふたのある容器に入れ、ハチミツをひたひたになるくらい注ぐ
3.ふたをして一晩おく。汁が上がってくるのでスプーンなどで静かにすくいとり、それを飲む
【れんこん湯】
〔材料〕
乾燥させたれんこん
だいこんあめ
〔作り方〕
1.乾燥させたれんこんの薄切りを煎じる
2.煎じ汁にだいこんあめを好みにあわせてくわえる
【せきたんの出やすい人は食事にも注意】
 豚肉は、食べ過ぎるとたんが出やすくなります。たんのからみやすい人や、熱があるときには、食べない方が無難です。
豚肉は、食べ過ぎるとたんが出やすくなります。たんのからみやすい人や、熱があるときには、食べない方が無難です。ナマコもたんが多い人は、多食しないようにします。
ぜんそくの人や、せきが出やすい人は、ブリの刺身を食べ過ぎると、発熱、たん、嘔吐などの症状が出ることがあります。素焼きか塩焼きにしたものを、少量たべましょう。
ほかにも、もち米やタケノコも、ぜんそくやせきを悪化させます。
参照:主婦と生活社「食べて治す医学大辞典」